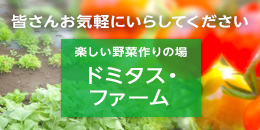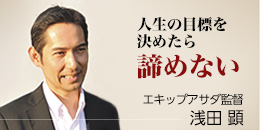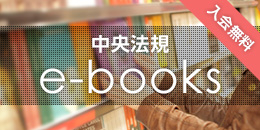|
日本民藝館は、「民藝運動」を提唱した柳宗悦(やなぎ・むねよし1889-1961)とその同志によって企画、実業家・大原孫三郎の援助を受け、1936年(昭和11年)に設立。民衆的工芸の美しさを再発見、それらを継承する作家育成の場ともした。
|
味わい深い瓦葺き屋根の建物。重い引き戸をゴトゴトと開けると、吹き抜けの天井、左右に伸びる大階段が爽快だ。玄関でスリッパに履き替える。ゴツゴツとした大谷石の素朴な感触が心地良い。館内を歩くと、階段の手すり、展示ケース、小椅子、障子の格子、電気シェード…どれも柳のこだわりのデザインが心にくい。
展示室に向かうと、美術館にあるべき「説明書」は、一切ない。
「事前の知識、情報による先入観を持たずに作品と向き合って、<直観>で美しさを感じ取っていただきたいのです」と学芸員・白土慎太郎さん。
<直観>は、柳が「モノ」と向き合う際、最も重んじたこと。東大で心理学を専攻、宗教学の教鞭をとり、神秘主義に傾倒、すべてに形而上のものを見た柳の生涯とコレクションを象徴する言葉だ。
 |
 |
本館1F、階段:玄関に立つと左右対称美がお出迎え。手摺の先のデザインは柳自身による。書は棟方志功。 |
本館1F、展示室:館内を彩る生花は民藝館ならでは。こんなさりげない演出にも敏感になりたい。 |
|
館内を彩る「モノ」は、どれも素朴な味わいを持つ。無名工人たちによる手仕事の日用雑器=下手物(げてもの)を「美」とし、機械製品の粗悪さを嫌う柳の「民藝運動」の美学は、今流行の持続可能で環境にやさしい「ロハス」な思想をも彷彿とさせる。 これぞ大衆に根付いた仏さま。ほっこりとした笑顔がありがたい。山梨の蒐集家の倉庫で偶然二体の木喰仏に出会い、ひとめぼれ。後、憑かれたように3年がかりで約350点を発見・調査する。 |
 |
 |
大らかな美を湛えるコレクションからは、政治意識も透けて見える。 柳が李朝工芸に傾倒するきっかけとなった作品で、館では格別大切にされる。「悲しみの白」「一抹の寂しさを漂へ…」などの語りは、韓国学者から「センチメンタルなヒューマニズム」「帝国主義イデオロギー」と批判もされる |
「民族」や「個」を重んじる意識は、沖縄民藝のコレクションにも見て取れる。
|
1940年、蒐集と調査研究目的の訪問の際、皇民化政策の一環である「沖縄語」の禁止、「標準語」普及運動を目の当たりにする。地元の言葉を話せないのはおかしい、素晴らしい文化をなぜ弾圧するのか。またもや新聞や雑誌で主張展開、物議をかもす。 南国ならではの鮮やかな発色は、地元の天然顔料の賜物。インドの更紗、中国の印花布、本土の友禅などの技術が相まって開花した沖縄の代表美。華やかな色彩と斬新な意匠は、芹沢銈介に多大な影響を与えた。 |
 |
創設70周年の2006年、『日本民藝館創設70周年記念特別展―民藝運動の巨匠』(7月4日(火)から9月24日(日))を開催。柳と共に民藝運動を提唱した浜田庄司、バーナード・リーチ、河井寛次郎等の作品200点を一堂に公開、その業績を回顧する。
また同期間、民藝館向かいの旧柳邸が修復工事を終え特別公開中だ。自ら設計し、72歳で亡くなるまで暮らした邸宅には、「美」に囲まれていなければ気のすまなかった男のこだわりの暮らしが垣間見える。この稀有な機会を見逃したくない。
 |
 |
旧柳邸:昭和10年、日光街道から移築された長屋門。後ろに見えるのは東大の先端研。 |
書斎:柳が多くの時間を過ごしたであろう一室。愛蔵本が今もなお書棚に並ぶ。 |
公開日:毎週水曜日(9月以降の一般公開は未定) 時間:10:30-16:00
 |
館内で一番多くの時間を過ごしてしまうほど、楽しい品揃え。ポストカード、手漉き和紙のレターセット、紅型のランチョンマット、刺し子のポーチ、中国のほうき、見ているだけでワクワクだ。 |
|
アートライター。明治学院大学大学院文学研究科芸術学専攻博士課程前期修了。専門は日本近世(江戸時代)絵画。その他、洋の東西を問わず美術、映画、音楽、演劇、文学など幅広く芸術全般に詳しい。
●URL● http://www.e-rena.net