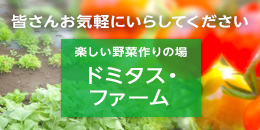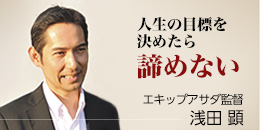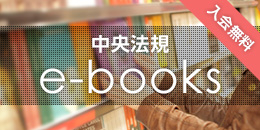- HOME
- 繋がる
- 年輪を重ねることはそれなりに愉しい人生
- Vol.3 伊達晟聴 氏
 |
|
 |
 |
「香道」とは、香りの芸術世界です。「香道」では「香りを嗅ぐ」といわず、「香りに聞く」といいます。心をこめて「香り」に聞くということです。人間の持つ「嗅覚(きゅうかく)」という本能を、心の世界へ高めた芸道といえるでしょう。
「香り」の世界に入った時、「香りに何を聞くことができるのだろう?」と自問自答したんです。香りに聞く世界を“聞香(もんこう)”といいますが、語源は「天帝に祈り、立ち昇る香のけむりに乗って願いを聞きとどけてもらう」ということです。
私は“聞香”という言葉に強く惹かれました。「そうだ、この“聞香”により、よき心を学ぶ術を託そう。そして、現代をたくましく生きる香りの世界を創ろう」そう思ったのです。
「香りに聞く日本のこころ、地球のこころ」、これが“香りに聞く知恵の道=聞香(もんこう)”です。
 |
「香木(こうぼく)」のことが、文献に最初に出てくるのは『日本書記』です。推古3年(595)に淡路島に流れついた木を、島の人たちが焚きますと、何ともいい香りが漂い、すぐに朝廷に献上されたようです。聖徳太子もこれが「沈水香木(じんすいこうぼく)」であることを知っておられたことでしょう。
「沈水香木」は、木に凝結した樹脂が香るのです。樹脂が深くついているものがよいとされます。「沈香(じんこう)」とも言いますが、水の中に入れると、すこし比重で沈みますので、この名がつけられました。
「香り」というのは人間の官能を刺激します。「匂い」の感覚は、大脳辺縁系というところでつかさどり、本能的な感覚に直接結びついているのです。「香り」は、昔から人々をワクワクさせたり、嫌悪させたりで、生命に直接関係していたのでしょう。宗教にも欠かせないものでした。儀式には、空間を清め、魂を清め、またグイグイと心の世界に入りこんで、人々を酔わせたんでしょうね。
唐招提寺を築かれた鑑真和尚が渡来された時、持参されたものの中に「薫物(たきもの)」があります。香木を粉々にして他の香も加え、蜜や梅肉で練り固めた「錬香(ねりこう)」です。これが平安時代には、王朝の雅(みやび)な香りとして、生活の中で愉しまれるようになりました。部屋に「空薫(そらだき)」、 衣服に「移香(うつりが)」です。
「たそがれどき」という言葉がありますが、「たがそれぞ」つまり、「ぼんやりとしたひかりの中、姿が見えるがはっきりと誰だかわからない・・・」という意味です。その時にフワッーとその人から香りが伝わってくるのです。着物に香りがたきしめてあるのです。「ああ高貴な香りだ。きっと光源氏さまに違いない!!」とわかるのですね。「錬香(ねりこう)」は、自分で調合できるので、独自な香りで着物を香らせることができるのです。
鎌倉時代から室町時代にかけて貿易が盛んになり、貴重な香木の量も豊富になりました。時代を担う武士たちが一木(いちぼく)の「沈香(じんこう)」をたいて愉しむようになったのもこの時代です。
「ばさら大名」といわれる佐々木道誉は香りが大好きで、香木をたくさん収集しました。室町時代、将軍足利義政が東山の銀閣寺で和歌や茶の会を催していましたが、その会から「香道」が始まったとされています。会所に集まった東山文化人は、香りを組み合わせ聞くことによって、和歌などの文学と結びつけ、主題をもった「香り」の世界を愉しみ始めたのです。この時代の人々の独創性は素晴らしいですね。ひとつの香味を味わい尽くす究極の香りと、主題をもって香りに聞くという世界へと香りが広がってきたのです。そして、江戸時代には、香りの作法も一般庶民まで伝わっていきます。現代では、アロマテラピーなどが注目されていますね。「香道」も最近では、少しずつ人気が高まってきています。
 |
今、学びの場を開いているのは、広島県竹原市の『医療法人社団仁慈会 安田病院』の協力を得て設立されたNPO法人『玄冬学舎』にて、その活動の中で「聞香研修会」を開いています。
会では、毎月主題をもって「香り」に聞いています。例えば、「聞香~香りに聞く平家物語」、「香りに聞く良寛の心」とかで、香りと心を合わせ、主題の中から生きる知恵を学んでいるのです。「香り」というのは、感覚ですから、静寂の中で一息一息(いっそくいっそく)、香りを聞きながら、集中力を培い、心を「無」にして、何がほんものなのかを正しく感じ取っていけたらと願っています。
例えば、『平家物語』だとしたら、最初に“祇園精舎の鐘の音・・・”という序文がありますが、その名文を味わい、扇の的・那須与一の物語をお話します。昔は、琵琶の音色が響くと、人々が集まり涙を流して聴いた、という世界です。戦国時代の武士たちも、琵琶法師を御前に召して語らせ、源平の人々の心中を追体験していたようですね。お稽古でも、琵琶の語りを聴いてもらい、香りと語りと調べで、全感覚を活性化するのです(♪~琵琶の音色が流れる)。つい、興がのってしまい、1時間くらい話してしまうこともあります。また、その話がとても愉しいと、皆さんはおっしゃってくださり、忘れかけた日本人の心をみんなで共有し合う大切な場になってきております。このように、和歌に限らず、古典などの物語の中に出てくる“人の心”を、「香り」を通して学んでいきます。
そして「物語の人たちの心はどうだったのだろう?」と「香り」に聞いていくわけです。その中に知恵を感じ取っていくのです。学ぶことによって、古人の持っている知恵を身につけることができるのです。つまり、“聞香(もんこう)=香りに聞く知恵の道”となるのです。この世の中で、どこかに素晴らしい出来事がある、素晴らしい人がいるかもしれないというのを「香り」で探っていけるのです。「香り」とは本当に奥深いと思います。
混沌極まれるこの時代に、ひと月に1回か2回、こういう感性を磨く場に出会っていただきたいと思っているのです。そして目的は、“そこはかとなく、香(かぐわ)しい人”になることです。
  |
『玄冬学舎』では、“心を磨き、命を育む”というコンセプトで“聞香”を行っています。いちばん大切なものは「感性=五感」ではないかと思います。21世紀は「知性の時代」ともいわれ、科学技術が発達しました。その中では、「見えるもの」をとても大切にしてきましたが、これからはもう一度、「見えないもの」の大切さに立ち返り、物事を考えることが非常に重要だと思います。知力のみが進み、感性がとり残されると、大自然とつながった人間の命の大切な部分が失われていくような危機感を感じます。感性が鈍くなると、何が起こるかというと、何か最近ちょっと憂鬱だなとか、かったるいなとか思ってくるのです。感覚が鈍っていて外部の世界が新鮮に感じられなくなってしまうので、心も暗くなってしまうのです。感覚を鋭敏にしたら、何かを見た時、ピピッと感じられるようになります。身の内も、外の世界も新鮮に感じ取ることができます。そこで、感性を磨いて、命を育んでいくのです。“安心立命(あんじんりゅうめい)” という仏教の言葉があるのですが、まさに“心を安らかにして、命を立てる” ように、これに通じると思います。
初めての人に「香り」を聞いた感想をたずねると、だいたいお母さんのことを想い出されるようです。子供の頃の記憶が一気にフワーッと想いだされます。「香り」は、心の開放にもなると思います。日常の心と同時に、大自然と結びついた「大きな自分=ほんとうの自分」とも出会えます。「香り」と一緒だから、大いなる記憶も呼び起こせます。確かに、「香り」は人間の記憶とよく結びついています。ですから、受験生が香りをたいて勉強していると、よく記憶に入るらしいのです。
また、「香り」は脳の活性化によい効果をもたらすといわれています。人間の脳にとっていちばんいいのは、「感動」することらしいです。感動すると細胞が活性化するのです。
「香り」を聞いて、物語を聞き、一気に感動することによって活性化されるのです。まず感性を磨いて、命をふたたびリフレッシュさせるのです。人間の脳には、右脳と左脳がありますが、香りを聞いて、そのイメージを言葉にする時、この右脳と左脳がクロスするのです。
この時に、法悦感に浸れるのです。今まで俳句も和歌を作らなかった人が、思わず感動で、詠じてみようかと思うのも、この時です。自分の感動を人に伝えようとするのは、「いのちの開放」です。これは素晴らしい体験といえるでしょう。
また、「香り」は一期一会です。同じ「伽羅(きゃら)」でも、その日、その時の香りなのです。火味の強さ弱さ、部屋の湿度、その日の主題、集まった人々の心、まさにその場の気配そのものの空気によって、香りの印象が違ってきます。これは、自然の恵み・香りのゆらぎをもつ香木から立ち昇る芳香だからです。この地球は、まさに「香りの星」といえるでしょう。
香道で使っているのは「伽羅(きゃら)」「羅国(らこく)」「真南蛮(まなばん)」「真那加(まなか)」「佐曽羅(さそら)」「寸門多羅(すもたら)」の6種類です。それに、「新伽羅」が入って7種類です。「香木(こうぼく)」は、日本では産しないです。インドからベトナムまでの東南アジアが産地です。これが、・・・・香炉です。香灰の入った香炉に、香炭団(こうたどん)をいけ(入れること)、灰手前(はいてまえ)によって聞き筋をつけ、雲母でつくられた「銀葉(ぎんよう)」をおき、その上に香木を乗せます。そうすると、香炭団で熱せられた香木から、香りがフワーッと香ってくるのです。
 |
聞香炉(ききこうろ)が1つ、香炭団(こうたどん)、銀葉(ぎんよう)、香灰(こうばい)、香箸(きょうじ)、火筋(こじ)、灰押(はいおし)、銀葉挟(ぎんようばさみ)を揃えれば、あとはお好きな香木を購入し、聞くことができます。
香りを聞く道具の簡単なセットは、香専門店とか、デパートのお茶道具コーナーで買い揃えることができます。(詳しくは編集部調べ参照)
香りを聞くことは、シニアの方でも簡単にできます。灰を扱う時、子供の頃の砂遊びを想いだされることでしょう。灰を扱って無心になるからです。筋目をつけるのですが、心が落ち着いてないと、筋がきちっと置けないのですが、すぐに体得されるでしょう。大切なのは、火味(熱加減:火の強さ弱さ)です。
アロマテラピーは、香りのもつ効果で、心身を癒したり、健康をもたらしたりすることでしょう。「香道」は、一木(いちぼく)の香りのもつ力を、精神性に高めました。また、「香り」と「文学」を結び、主題をもって「香り」に親しむ日本独特な文化を育てました。世界でも類のない日本の伝統文化だと思います。
20代から80歳くらいの方まで比較的年齢層が幅広いです。例えば、『平家物語』などの文学は、中学の頃学んだ記憶があって、今ではよくは知らないけれども、どこかで記憶の片隅にあるわけです。お話を始めると、それが一気に昔に遡って想いだされるのです。
広島県の『安田病院』の介護老人保健施設『まお』では、毎月地域の社会福祉の方々と共に、「香の会」が開かれています。その会では、唱歌を歌って香りを聞いていただいています。
私は若い時に、出版関係の仕事をしていたのですが、「香道」の先生から本を作って欲しいと依頼されたのが「香道」に入るきっかけです。もとから文学が大好きだったのですが、それが香りと結びついたのです。『古事記』『日本書紀』『万葉集』『竹取物語』や『源氏物語』に始まって、『古今和歌集』など、主題となる香りの世界を組み創造していけるとは、こんな愉しいことはありません。そして、心がドキドキするようなテーマで「香り」を炷(た)きたいと思いました。それが、“聞香(もんこう)”を始めるきっかけです。
 |
私の場合は、仕事(=香り)ばっかりなんです。街を歩いても香りでしょ。イラク戦争をテレビで観ていても、「ブッシュさん、フセインさん、共に香りを聞きませんか?」と思います(笑・・)。すべて香りに結びついてしまうのです。こういう素晴らしい香りがあることを、全世界の人々に知ってもらいたいと思います。
物語の世界は宮沢賢治をやって、釈迦やイエスをやって、ジョン・レノンのイマジンまで広がります。そんなことを考えたら、普通の日も全部「香り」につながってしまうのです。見たこと、この世の出来事、生活すべてが「香り」なのです。それを、愉しんでいるんですね。
私にとっては「香り」を通して、自分の人生観を物語の中で語っていくことだと思います。すべての人生経験が古典文学の語りに入っていき、香りに結びついて、初めてその物語が生きてくるような気がします。それが、自分の人生の使命であるような気がします。『平家物語』の「諸行無常」とは、「常ならず」ということですから、今、悲惨な状態でも素晴らしい状態になれるということです。「全ての万物の行いは変転していく=はかなさ」と捉えるのか、「どんな時でも次がある=生の躍動」と捉えるのとでは、自分の人生を考えてみると違うぞ、と思ったのです。「もう一度、立ち直ってみよう」と思った時に“諸行無常”という言葉がものすごくポジティブに話せるんです。語りのイメージの中にそれぞれ自分の人生が重なり、それが「香り」に乗ってくるのです。
そして、私がいちばんやりたいことは、皆さんと共に、香りにのって「勇気」をもらうことです。自分の心を表現して語り合う時間は必要なことだと思います。「香り」はその1つのきっかけです。
座ることばかりですので、まず、歩くことをしています。歩くこと、歩くこと、それしかないですよね。
先日、図書館から帰ってくる途中、交差点でぱっと空を見上げたら雲がかかっていたのですが、明るい空が見えたらちょっとのことで幸福感がありました。日頃、釈迦とかイエスを勉強していると、雲がそれに見えたりして・・・(笑)。“聞香(もんこう)”をやろうとして、やっと自分の使命が見えてきてつくづく幸せだなあと思います。そうすると、ストレスがないんです。眼科に行った時も、お酒をやめてストレスをためるより、お酒を飲んでストレスがないほうが眼にはいいですよ、と女医さんに言われました。
若い時に知っていたら、自分の人生が変わっていただろうと思う言葉に“足(た)るを知る”という老子の言葉があります。小さな我欲を持つということはあまりよくないのです(笑)。人生は大いなる欲をもって、この世のために自分を捨てることができれば、こんな素晴らしいことはないですね。中途半端な欲をもつと、それが、ストレスになるのですから。若い時にはまだまだ、欲しいものややりたいことがあるかも知れませんが、今の時代だからこそ、若い人たちにも必要なことだと思います。
それと、ポジティブに生きることです。今しかないんですから。過去も未来もないのです。ただ、“今”あるのみなのです。小林正観先生も仰られています。「ほんとうの意味の刹那に生きることです。全力で!!『西遊記』の主人公、唐の玄奘(げんじよう)(三蔵法師)が、行きは15年半かかるけれど、帰りは1年半で帰ってくるのです。なぜかというと、途中で色々な頼まれごとをされるのですが、彼は絶対断らないのです。自分の大切な任務があるにもかかわらず、目の前で自分を頼りにした人に対しては、その場で真心で答えていこうとしたのです。今、この瞬間が大事だから、目の前の人を大切にしようと思ったら15年かかってしまったのです。帰りは知り合った人たち皆が協力してくれたおかげで早かったのです。これは、今の瞬間がいかに大切かということと、人に尽くすことの大切さの教えでもあるのです。」
人に尽くすことは心が晴れ晴れすることでもあるのです。「慈悲」ということが仏教では大切なのですが、人の悲しみに出会った時、その人の悲しみよりもっと深い慈しみの悲しみで包み込むことができれば、お互いに勇気が湧いてくるものなのです。自分の人生は未来に開かれているんだということです。いい未来を選ぶことが勇気を与えるのです。以前CMに“今、世界が始まる”というのがありましたが、これだと思います。今までの苦しみを全部捨てて、今世界が始まっていくんだと考えるのです。そこから、未来が開けると思います。
 |
宮澤賢治の『十力の金剛石』という童話に書いてあります。二人の少年が金剛石を探しに行くのですが、森に入っていくと、帽子の飾りの鳥が、突然飛ぶようになり道案内をしてくれます。いつの間にか、森に囲まれた丘の上に出ます。さきほどからの雨が、あられに変わりました。二人は驚きました。あられと思ったのは、実は、宝石だったのです。地面に落ちたら、カチンカチンと音がするのです。「どうして、音がするのだろう?」見ると、地面も、咲いている花も草も、宝石でできている丘だったのです。
あまりに美しいので、すぐに持って帰ろうとハンカチを開くのですが、もう持って帰るのもいやなくらいにすべてが光り輝いているんです。ところが、野ばらの木が悲しげな歌を歌うんです。「ひかりのおかのこのさびしさ」と・・・。そこで「どうしてそんなにかなしいの?」と聞くと、「十力の金剛石は今日も来ない・・・」と言ってまた泣くのです。
しばらくして、「十力の金剛石がとうとう下った」と花が叫びました。すると、花や草など、丘のすべてのものがほんとうの花や草になるんです。
そして、十力の金剛石は、露だったのです。つまり、宝石よりも、ほんとうの花の素晴らしさとか、生命の素晴らしさをそこで教えてくれるのです。
このお話のように、人間もほんとうの自分を生きるのがベストだと思います。
人間は、色々な自我(肩書き)で固めているけれど、「ほんとうのもの(生命)」になって生きていけたら、こんなに楽で素晴らしく、愉しいことはないと思います。
“深香如意(しんこうにょい)”という言葉を、真言宗高野山の『吉住明海和尚』からいただいたのですが、「深く香りに聞いて意の如く生きよ」ということです。「香り」というのはそれぞれの人がそれぞれに聞くのです。“意の如く”というのは、自由自在に生きようということです。“いい加減”という言葉がありますが、例えばお風呂でも熱くもなく、ぬるすぎもしない“いい加減”のお風呂に入りたいです。人生もそのように生きられたら最高なのです。仏教では“中道”として極端に走らないことを教えています。
深く「香り」に聞いて自分の心を開放して、自由自在に生きられたらこんな愉しいことはないのです。
|
日本の伝統文化の継承と新しい文化の創造の活動を通して、社会の福祉に貢献することを目的としたNPO法人『玄冬学舎』にて「聞香研修会」を開催。全国各地で講演会および“聞香”の指導をしている。 |
|
“聞香(もんこう)”を受講されたい方は、こちらまでご連絡ください。 |
|
|
■香を聞く、簡単な香道具について(編集部調べ) |
年輪を重ねることはそれなりに愉しい人生
- Vol.24 浅田顕 氏
後藤義治 氏 - Vol.23 萩原 かおり 氏
- Vol.22 堀江眞美 氏
- Vol.21 原田忠幸 氏
- Vol.20 齋藤佳名美 氏
- Vol.19 花れん 氏
- Vol.18 宮澤崇史 氏
- Vol.17 常磐津千代太夫 氏
- Vol.16 尹貞淑 氏
- Vol.15 土屋郁子 氏
- Vol.14 内野慶子 氏
- Vol.13 浅田顕 氏
- Vol.12 桜林美佐 氏
- Vol.11 出石尚三 氏
- Vol.10 只浦豊次 氏
- Vol.9 和田三郎 氏
- Vol.8 小林洋 氏
- Vol.7 永井明 氏
- Vol.6 ラモン・コジマ 氏
- Vol.5 母袋夏生 氏
- Vol.4 吉村葉子 氏
- Vol.3 伊達晟聴 氏
- Vol.2 辺真一 氏
- Vol.1 柳澤愼一 氏
年輪を重ねることはそれなりに愉しい人生
- Vol.24 浅田顕 氏
後藤義治 氏 - Vol.23 萩原 かおり 氏
- Vol.22 堀江眞美 氏
- Vol.21 原田忠幸 氏
- Vol.20 齋藤佳名美 氏
- Vol.19 花れん 氏
- Vol.18 宮澤崇史 氏
- Vol.17 常磐津千代太夫 氏
- Vol.16 尹貞淑 氏
- Vol.15 土屋郁子 氏
- Vol.14 内野慶子 氏
- Vol.13 浅田顕 氏
- Vol.12 桜林美佐 氏
- Vol.11 出石尚三 氏
- Vol.10 只浦豊次 氏
- Vol.9 和田三郎 氏
- Vol.8 小林洋 氏
- Vol.7 永井明 氏
- Vol.6 ラモン・コジマ 氏
- Vol.5 母袋夏生 氏
- Vol.4 吉村葉子 氏
- Vol.3 伊達晟聴 氏
- Vol.2 辺真一 氏
- Vol.1 柳澤愼一 氏